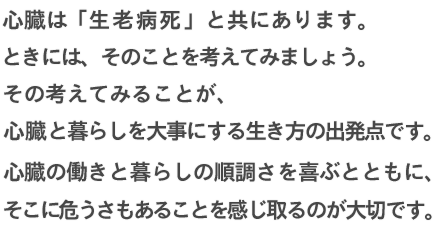
これらの文章は、2002年から2003年の岩手日報コラムに連載されたものです。
今でもとても面白く読めましたので、再掲載しました。 ぜひ、ご一読ください。
 |

第9回 「病気のリスクにどのように備えるか」岩手医科大学第二内科・循環器医療センター 前回は、患者さんもリスクを引き受けなければ医療は成り立たないという話を書きました。 企業のリスクマネージメントの本に、こんな話が載っていました。 「具体的なリスクがあると認識できれば、リスクマネージメントの7割は終わっている」 と。 病気や死は、いつ襲いかかるのか予想できないものです。生命保険や疾病保険はリスクを分散させるために、健康なときに小額のお金を毎月かけて、いざというときの資金不足というリスクに備えるものです。 これまでの連載で触れてきたように、生活習慣に関係のある病気への対策をしっかりすることで、多少のリスク回避は可能です。しかし病気がまだない人にも病気は襲ってきます。ときには、リスクを正確に理解する心の余裕もないまま、そのリスクを引き受けなければならないときもあります。 具体的な例で考えてみましょう。 急性心筋梗塞症という病気のことです。前触れなく中高年を襲い、冠状動脈がふさがれて心臓の筋肉が一部動かなくなり、急性期(約1ヶ月)をすぎても心臓の機能障害という後遺症を残すことがある病気です。 かつての治療法は、できるだけ安静にして心臓への負担をさけ、急性期をしのぐという、いわば消極的なリスクマネージメントが主流でした。 
それが、1980年代になり、先端に直径2mmから3mmの風船(バルーン)がついたカテーテルという管を血管の中に入れ、ふさがった冠状動脈を機械的に広げる治療(PTCA)ができるようなり、積極的なリスクマネージメントへと治療法が変わってきました。 しかし、この治療法は冠状動脈を破裂させたり、冠状動脈の中に血塊ができ、状態がかえって悪くなるなどのリスクを伴うものです。それでも、そのリスクを引き受けていただけるなら、後遺症を残さない社会復帰も可能になります。 さて、急性心筋梗塞症になった患者さんの多くは、胸が苦しくて、死ぬかもしれないという恐怖に襲われています。そんなときに説明を受けて、治療のリスクを正確に理解するのは非常に難しいことです。 治療のリスクを引き受けず、ただ静かに休んでいて、嵐が去るのを待つという選択肢もあります。救急治療にあたる医師としては、最新の技術で最善を尽くしても、うまくいかなかったときのリスクを引き受けて欲しいという気持ちがあります。しかし実際にはそれが難しい。ここに現代の医療のジレンマがあります。 望ましいのは、いつも診てもらっている医師と良好な関係を築いて、どのようなリスクがあるのかの情報提供を受け、それをあらかじめよく理解しておくことです。医師にかかっていない人でも、病気のことや治療法を知る手段は、インターネットやテレビや雑誌など、いくらでもあります。急場になって医師の言うなりの治療を承諾し、治療が不成功だったときに、「自分が思っていたのと違う」といっても遅いことが少なくないのです。 大切なのは、健康なときから、自分にありうるリスクを知っておくことです。いたずらにリスクを恐れず、冷静にこれに対処する人には、最善を尽くして応えてくれる医療があります。たとえ治療がうまくいかなかったときでも(それがリスクですから)、これは自分が覚悟して選択した治療の結果だということで納得しやすいのではないでしょうか。 第9回 掲載:2002年11月5日 当ページは岩手日報社の許可を得て掲載しています。 |



 前
前
